今回は内村鑑三(1861〜1930)の『宗教座談』という本を紹介します。内村鑑三はキリスト教の思想家、文筆家、伝道者で自身もキリスト教徒としてキリスト教を深く信仰していました。
はじめに
昔から何かを「信仰」するというのはどういうことなのだろう?という素朴な疑問がありました。
その疑問を初めて抱いたのは、まだ幼い頃に四九日かなにかで祖父母の自宅にお坊さんが来たときです。仏壇のある狭い和室の中に黒い服をきた大人と子供がぎゅうぎゅうに入って、お坊さんの唱える呪文のようなものをみんなじっと静かに聞いている、そうした姿が日常とはあまりにかけ離れていたため今でも頭に残っています。
だから宗教というと頭に思い浮かべるのはそうした一時的な儀式やイベントのようなものが多くて、きちんと「信仰」と呼べるような宗教体験はしたことがありません。
そこで、今回は近代にキリスト教の「信仰」の世界に深く入り込んだ内村鑑三が書いた『宗教座談』を通して何かを「信仰」するというのがどういうものか考えてみようと思います。
この『宗教座談』の表紙に載っているあらすじをまず紹介します。
「私は教師でも牧師でも神学者でも何んでもありません」。内村の思想・行動の中核をなす信仰とは学問的真理ではなく、自身の生に根ざした「事実」であった。なぜ信じるのか、なにを祈るのか(以下略)。
内村にとってキリスト教は学問でもフィクションでも儀式でもイベントでもなく、まぎれもない現実であり事実でした。日常生活そのものがキリスト教だったと言ってもいいかもしれません。なんの肩書きも関係ないと言う内村の言葉はキリスト教徒や特定の宗教を信仰していない私にとって、「信仰」ということを身近に教えてくれる先生のように思えました。
生涯を通じて一人のキリスト教徒として神への信仰と向き合い続けた内村鑑三のこの本からキリスト教における信仰するということがどういうことなのかを考えていきます。
神を信仰するのに教会はいらない?
キリスト教といえば教会のイメージが強く、まずキリスト教徒の信者は日曜日になると教会に出かけてそこで祈りを捧げる、というイメージが強いですが、内村は当時の教会のあり方をあまり良くは思っていなかったようです。
この章のなかで内村鑑三は教会のことを辛辣に非難しています。その言いっぷりを見ているとかなり激しく教会に対して反発したようです。おおまかにその内容を意訳すると、
「教会は本来の教会がするべき人々の魂を救うということを忘れてただの社交と慈善事業を勧めるだけの場所に成り下がっている。だから世間に色気を出すことになるし、そういう風だから俗物ばかりが集まってくるのだ」
内村自身がストイックで誰よりも熱心な信者だったからこそ、たとえ信者を増やすための教会なりの行動だったとしても、本来の神の教えとはかけ離れた›ものに感じて許せなかったのだと思います。内村の最初の著作の『基督信徒のなぐさめ』(1893年)では内村は既存の教会と離れてしまった自分のことを次のように書いています。
余は無教会となりたり。人の手にて造られし教会今は余は有するなし。余は慰むる讃美の声なし。余のための祝福を祈る牧師なし。さらば余は神を拝し神に近づくための礼拝堂を有せざるか。
簡単に意訳すると、「私は無教会となりました。人の手で造られた教会持たない私には、私の心を慰めてくれる讃美歌は聞けない。私のために祝福してくれる牧師もいない。それならば私には神に祈り、神に近づくための礼拝堂をまったく持っていないのだろうか?(いや、そうではないだろう)」
そもそもキリスト教徒になるためには必ず洗礼を受けなければなりませんが、だからといって信仰するのに教会は絶対に必要かというとそうではありません。毎週日曜日に教会に行くから熱心な信者かと問われると疑問符がつきますし、教会に行かないからといって信者ではないかというと違う気がします。
そのことに対して内村はたとえ物理的な教会がなくても、自分の心の中に教会があればいいのだ、と言います。場所などは関係なくそれぞれが自分の心の中に築いた教会の中で神に向かって祈りを捧げればいいのだと。
聖書の正しい読み方

私自身は聖書を読み通したことはないのですが、聖書にはちょっと気軽には読めないような神聖で難解なイメージがあります。けれども内村はこのイメージの両方を壊していきます。
まず、内村は聖書そのものを信仰の対象にしてはならないと言います。聖書は神が自ら書いたものではなく、人の手で書かれたものだから、その点では他の書物と大差はないし、だから文章の中に矛盾や間違いもあるのだ、とさえ言って聖書そのものを神聖で崇拝するべきものとして考えることを否定します。
聖書を読むには押さえておくべきポイントを内村はあげています。
- 聖書は人間を助けるために神が過去から未来までの手順を書いた本
- 聖書はイエス・キリストの伝記
- 聖書は神について書いた本
この点を押さえて読めば聖書は決して難解ではないと内村は言います。何が書いてあるのかさっぱりわからないまま読もうとすると聖書でなくても内容が頭に入ってこないですよね。読む前に書かれてるあらすじを読んで読むべきポイントをきちんと整理しておけば、たしかに読みやすくなります。
また内村は聖書を理解するには手順があり、まずは聖書を読む前に神を体感するという体験こそが大事だと言います。
聖書を真正(ほんとう)に読もうと思えば我々は直接に神の感化を受けねばなりません、神は聖書よりも大なる者であります、故に聖書に書いていない事をも神は我々の心に告げ給うことがございます、我々はまず直接に神より聞かねばなりません(中略)、まず祈祷を以てじかに神に接し、じかに神の言辞(ことば)を心に受けませんならば我々は聖書すなわち神の言辞であるという事が解りません。
ちょっと内容が難しいので、別の話にたとえて考えてみます。
恋愛小説を読んだとき、もしもその小説を読む前にあなたが実際に誰かを好きになった事なんてなかったとしたら、その本がどれだけ素敵な恋愛小説だったとしても、本当に共感を持って理解できた、とは言えないと思います。
好きな人のことを考えたときや目の前にした時のちょっとした気持ちの揺れ動きや、失恋した時の絶望感、嫉妬、憧れ、焦燥感など、そうした実際に過去に体験したことを本の文章を通して一緒に共感できるからこそ、その小説に感動したり、楽しめたりできますよね。
私は内村が聖書に対してここで言っていることもその感覚に近いと思います。
聖書を読んでも神に出会えることを期待したり、感動するのを期待してもそれは難しいのです。まず自分が神に出会い、その上で同じような神の出会いとその奇跡を体感した物語が書いてある聖書を読むから、共感できたり、感動できるのだ、ということなのだと思います。
聖書の役割とはあくまで補助的なものであって、聖書がなくても神を知ることはできるのだと内村は言います。
聖書なしに神を見るのは丁度朧月夜に月を見るようなものでありまして、見ることのできないものではありませんが、ただボンヤリと見えるだけでございます。
つまり聖書を読むこととは自分が直感的に体験した神の曖昧なイメージの原石をはっきりとした形にカッティングされた宝石に仕上げていくような作業なのです。
神を知るための手順を簡単にまとめると、
①日々の信仰の中から、②神を知るという体験をし、③聖書で神がどういう方なのかを確かめていく、という順になっていきます。
キリスト教徒は繰り返し聖書を読みます。その過程の中で、本来は信仰するべき対象であったはずの神をおろそかにしてしまって、聖書そのものを信仰してしまうことを内村は注意しています。
似たようなことは私たちにもあって、本来の目的を実現するための手段であったはずのことが、逆転してしまい手段が目的化してしまうことは仕事や日常生活の中でよく起こります。そうした状況に陥らないためにも、内村はここで聖書の読み方と優先順位を整理してくれています。
内村鑑三にとっての祈りのかたち

「祈り」という行為は考えてみると不思議な気がします。宗教にとって祈るという行為は重要視されていますが、特定の宗教を持っていなくても、祈ることを自然とする人も多いように思います。
私も道端にあるお地蔵さんに頭を下げたり、神社や寺に行けば参拝したり、道路沿いに花束を供えてあるのを見つけると手を合わせたりします。一口に「祈り」といってもいろんな形が存在しますよね。
ではキリスト教における「祈り」とはどういう行為なのかというと、ひとことでいえば「感謝」なのだと内村は言います。少なくとも健康祈願、安産祈願、合格祈願など何かがうまくいくようにと、神にお願いするような行為ではないようです。なぜなら神はこちらが祈ろうと祈るまいと関係なく、試練も恩恵も私たちの願いや意思に関係なく神の意思によって与えていくからです。
私はまず満腔(まんこう)の感謝を以て私の祈祷を始めます、私はかくも麗しき宇宙に生を賜し事について私の神に感謝致します、私は私に良き友人を給いし事について、私に身を委(ゆだ)ぬべき事業を与え給いし事について、私に是非善悪を判別して正義の神を求むる心を与え給いし事について、殊に私が神より離れて私利私欲をのみ追求せしに当て私の心に主イエス、キリストを現わし給いて私の霊魂をその救済の途につかしめ給いし絶大無限の恩恵について深く感謝致しまする。
※満腔ーからだじゅう。満身。
もし「願い」が未来に向かって何かを保障してもらうことを望む行為なのだとしたら、キリスト教の「祈り」とは過去にすでに与えてもらったものと、そのおかげで現在自分がこうして存在することに対する感謝の行為なのだと言えるのかもしれません。
見返りを求めず、神が自分の「祈り」を聞いてくれているかどうかも期待しない。内村にとっての祈りとは孤独に慎ましくひたすら神と向き合う行為なのだと思います。実際に内村は教会で神父や信者と一緒に祈るのではなく、静かな一人になれる場所に出かけて、そこで感謝の祈りを捧げていたようです。
信仰とはこうした祈りの積み重ねによって幾重にも編まれた綱のように決して切れない神への信頼感を強く、太くしていく行為なのかもしれません。
信じて論理を超えた先に飛び込め
まず「信じること」、これがキリスト教の最も根幹にあるのだと思います。しかもそれは言葉だけの生半可なものではなく、それこそ「頭の天辺から足の爪先まで」、「骨の髄まで」、「全身全霊で」信じなければいけません。これは簡単そうに見えて本当に難しい。
私はこのことを考えていたとき、映画の『インセプション(2010)』のワンシーンを思い出しました。
この映画は人が眠っている間に潜在意識に侵入し、他人のアイデアを盗み出すという、現実と夢の中を行き来するというSFアクション映画です。そのシーンでは主演のディカプリオ演じるコブとマリオン・コティヤール演じるモルの夫婦が出てきます。
彼らは夢の世界の中で50年もの長い間、自分たちの理想の世界をつくりあげるという壮大な実験をしていました。ところが現実に帰ってきた時にはモルは現実と夢の世界の区別かつかなくなっていました。
モルは現実の世界に返ってきたにも関わらず、現実を夢だと思い込んでしまいます。現実の世界へ戻るためには夢の中で死ぬことが必要なのですが、そのことが悲劇をうみます。
2人の結婚記念日にコブがお祝いのために予約したホテルの部屋に帰ってくると、部屋の中は不自然に散乱していました。コブが不審に思い、モルを探すと、モルはホテルの窓枠に体を外に投げ出した状態で座っていました。
「私と一緒にここから飛び降りて」とコブに語りかけます。コブは今の世界が現実だと知っているのでモルを必死で止めようとします。しかしモルは今の世界が現実ではないと思っているのでコブの説得に聞く耳を持ちません。「私を信じて飛ぶのよ」とモルは今にも飛び降りそうになりながらコブを追い討ちをかけます。
『インセプション』のこの息を呑むようなシーンでは結局コブはモルと一緒に飛び降りることを選択しませんが、「信じる」ということを考えたとき、このシーンはとても象徴的なように感じました。自分が正しいように思えたとしても、相手が間違っているように感じたとしても何を犠牲にしても相手のことをまるごと信じる。それほどの覚悟と信仰心が必要だと内村鑑三は言っているように思います。
実際、モルがこのシーンで言う「私を信じて飛ぶのよ」というセリフは英語では「take a leap of faith」と言っています。これは、(決断などで)論理を超えた判断(信じて思い切ること)が必要である。という意味になります。
内村が言うところの信じるとは、この「take a leap of faith」の意味が指すような、正しいのか?間違っているのか?といった論理や疑問を飛び超えたところにあるものなのじゃないかなと、思います。これほどに神に全てをゆだねて「信じる」ということができたとき、キリスト教の世界はブワッと目の目に開けてくるのではないでしょうか。
最後に
この本を読むまでは、内村鑑三が何をした人か、というのは学校の教科書に出てくるぐらいの知識はありましたが、内村がキリスト教をどのように「信仰」していたのかは知りませんでした。
この本は内村自身の言葉で「信仰」するとはどういうことなのかを丁寧に説明してくれています。本のタイトルが『キリスト教座談』ではなく、あえて『宗教座談』としているところにも何か「信仰」するということに対する内村なりの普遍性を見たのかもしれません。
私も特定の宗教を信仰したことはこれまでありませんでしたが、宗教というのは多かれ少なかれ必ず人生の中で触れるものです。キリスト教を信仰するということに自分の人生をかけて誰よりも真摯に取り組んだ内村のこの本を開いてみて、あなたも「信仰」という、普段は触れない世界を少しだけ覗いてみてはいかがでしょうか。
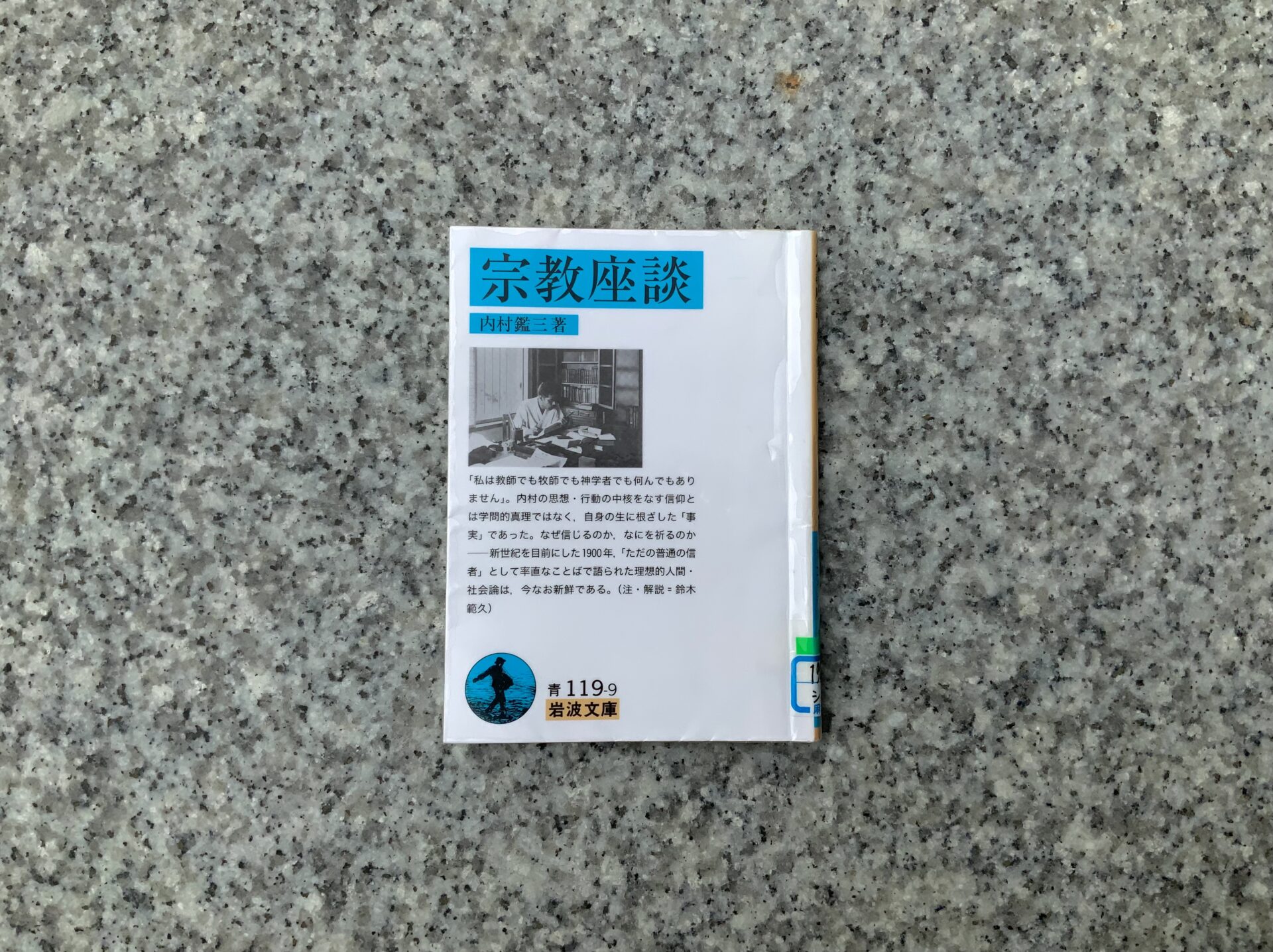






コメント